|
SpecialSweetStupid 11月6日の「土銀よろしくお願いします」で無料配布した小冊子のSSです。 全部土銀ですが、学生とか本編沿いな感じのとか結構ごちゃまぜですので気を付けてください。 ツイッターでリクエストくださった方、ありがとうございました! 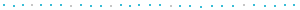 クラスが離れて、初めてのテストが終わった。お互いの答案用紙が屋上のコンクリートの床に広がっている。 「なんかお前、成績上がってない?」 「そうか?」 風が吹いて飛んで行きそうになる答案を捕まえて、銀時は皺を広げて点数を読み上げる。 「八十二、八十五、これなんて九十じゃねーか! もしかして学年トップ二組にいるって、お前のこと?」 「違うと思う、けど」 「まあそれでも十分すげぇけど。どこの大学行くつもりだよこの成績、国立? 有名私立?」 「まだ決めてねーっつーんだよ」 銀時は自分の答案を隣に並べて、無言でしかめっ面をする。そこまで悪い成績ではないし、まだ一学期だ、十分巻き返せるし、 銀時は部活に入っていないのだから、自分よりずっと時間もある。 「どうとでもなるだろ」 「どーだろうなー」 今度は答案を飛んでいかないように鞄の下に挟みこんで、銀時は立ちあがる。からりと晴れた空に、大きく伸びをして、フェンスの方へ歩いて行く。 その後ろ姿は、一緒のクラスだった去年とまるで変わらないようにも見える。 最後の一年を、同じクラスで過ごせなかったことはやっぱり、何度考えても残念ではある。 だが、こうして落ち合って、お互いの知らないクラスのくだらないことを話すものなかなか楽しいものだと、最近では思えるようになった。 「なんでそんな成績上がってんだよ、くっそ」 錆びたフェンスを掴んで、前後に揺らしながら銀時は叫ぶ。グラウンドから聞こえる、野球部だかサッカー部だかの声に混ざってかき消される。 「部活もやってんのになんなんだよ土方ぁあぁぁ」 今日は明日の学校行事のために体育館が使えないから、部活は休みだ。こうして銀時と一緒に居られる少ない時間を得て、正直とても嬉しかったりもする。 「……別のクラスになったからな」 「だからなんだっつーんだよー」 ぶすくれた銀時の顔がこっちを向く。同じクラスだった時はこいつの一挙手一投足が気になって、授業中の横顔だってじっと見ていたせいだ。 それがなくなったのだから、成績の一つや二つもあがるってものだろう。 「お前があんまりいい大学行ったら、俺の頭が追いつかねーからあんま勉強すんな!」 「……同じ大学行くつもりなのか?」 「そーだよわりーか!」 赤い横顔に悪くない、と笑って、答える。 (同級生土銀) 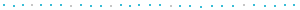 玄関の戸に背中を凭せかけたら、ぎいと嫌な音がしたのであわてて背中を離した。 その挙動が可笑しかったのか、すぐ隣の土方はくっと可笑しそうに喉を鳴らした。 足元には簡易な敷物とツマミと酒。玄関出てすぐの外廊下に、二人して座り込みで飲み会だ。馬鹿馬鹿しいことこの上ない。 「ああ、もう酒がねーな」 「中から取ってくるわ、それか、買いに行く?」 「そうだな、買いに行くついでに、散歩でもするか」 珍しく酔狂なことを言う土方は、もう酔いが回っているのか、それとも今日は新月だから何かおかしな力でも働いているのか。 新月のおかげで、星がずいぶんと明るくて綺麗に見える。それがそもそもの始まりで、あんなところで飲む理由だったのだ。 敷物から立ち上がると、そのままそれを玄関に引きずり込んでとりあえず片付けて戸を閉める。階段を降りる脚はお互いにおぼつかないが、 それも酔いのせいだか、新月の暗さのせいだか判別がつかない。つけようともしていない。 一番近くのコンビニに向かってどちらともなく歩き出す。ぼんやり空を見上げながら歩いていると、土方がすいと手をあげて指さして言う。 「カシオペア」 「……星座?」 「そう、あっちが白鳥、だったはず」 「ふーん、意外だな、そういうの知ってるの」 「昔な、聞き齧っただけだ」 「俺は、ギョーザにピザしかわかんねーわ」 「ガキか」 少し立ち止まってくっくと声をあげて、さぞ可笑しそうに土方は笑った。その一歩前から、銀時は土方にゆっくりと手を差しだす。 「星同士繋ぐよりももっと、俺としては繋いでほしいもんがあるんだけど」 「わがままな星もあったもんだな」 土方は一歩進んで隣に並ぶと、その手を繋いだ。再び歩き出す速度は、きっとどこかで流星が燃え尽きるように、 早くも遅くもあった。ただ、その手は夜の中にあっても、太陽のように確かで暖かい。 (秋の夜長) 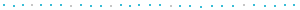 雪が降って来ないのが不思議なくらい、寒い日だった。空気が凍りついて、塊になって崩れ落ちるんじゃないだろうかと、銀時はふとそう思う。 ばきばきになった世界はさぞかし猥雑で面白いことだろう。元から汚いかぶき町なんて見ものにちがいない。 喉に滲みるくらいの外気を吸いこんで、息を吐くと真っ白な息で目の前が曇る。鼻の頭がつんと冷たい。 なにもこんな日に限って、冷蔵庫の中身が空っぽになる必要もないだろう。昨日は比較的暖かかったのに、今日は一転してこれだ。 明日も寒いらしいのでどっちにしろ寒い中買物に行かねばならない。 かじかむ指先を擦り合わせて、さして暖かくもないポケットにつっこんで、再び歩き出す。 竦めていた首を少し伸ばせば、見覚えのある黒いコートが見えた。この曜日この時間なら、ここを巡回で通ることなどお見通しなのだ。 さて何をたかってやろうか。買物に行くはずなのに、ほぼ空っぽの財布の中身だろうか、やっぱり。 なるべく足音を消して、そっと後ろから近づいて行ったが、どうやらその前から気付いていたらしく、あっさり振り返られた。 「なんか用か」 「腹減った」 「……どうせまた依頼がねえから、金もねえし食料もねえってんだろ、もうちょっと計画的に生きろ」 「そんなこと、できるんだったらやっとるわ」 土方の歪んだ顔を、ポケットから出した両手で挟んでやる。さすがに顔の表面は手よりも冷たい。温度がじわりと滲みていく感覚がする。 「晩飯、お前の好きな鍋にするから、金ちょうだい」 「お前なぁ、もうちょっと言い方ってもんがあんだろ」 呆れながらも、土方は財布を出してくれることを知っているのだ。 こうやって間抜けと言えるだろう、土方の頬を挟んでいるこの格好のまま、世界が凍りついて、自分達も凍りついて崩れ落ちてしまっても、 たぶん後悔はしないだろう。そんなことを思いながら、土方の頬からゆっくりと手を離してやるのだ。 (真冬のすごく寒い日) 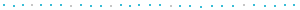 この間土方が家に来た際に気にいらないことを言って帰って行きやがったので、今さっき真選組に行ってケンカを売って来た。 が、あいにくいなかったので、置き手紙とジミーに言付けだけして帰って来た。 自室で寝ころんで、壁に足の裏をくっつけてみる。そのまま開けっぱなしの襖の向こうに見える、ひっくり返った居間をぼんやり視界に移して考える。 何度めのケンカかすら忘れてしまった。大体、そういう相手がきっとむっとするであろうことを簡単に口にして、 こっちがひっくり返った心を立て直す前に自分勝手に出ていくのだから、ケンカを売り返されたって仕方がないだろう。 「期待してねぇってなんだよこのクソ野郎」 離した踵で、壁を蹴ろうとしたが、ヒビでも入ったらことだからやめる。 途中まで勢いよく下ろしかけていた足を、ゆっくりにしてまたペタリとくっつけて、まとまらない考えを何度も逡巡する。 確かに何かやれるような性格でも生活でもないけど、それでもこっちを選んだのは土方だ。 こっちだって別に何も見返りなんて欲しいわけでもないのに。ただ、結構好きだとかそういう、そういうことを思うだけで。 「こういうことを言えば良いわけか……?」 でもたぶん言えないし、言わないだろう。それこそ期待されてもいないことだ。 だんだん、と階段を上ってくる音がする。そら来た。絶対にこの足音は土方だ。深く息をして、待つ。 勢いよく、しかも何の躊躇もなく開ける戸の音、踏み込んでくる革靴の音、そして。 「おい銀時ィいんだろコラァ」 さあたった一つ確かにやれるものをやろう。ケンカだ。実になるのかならないのか、そんなことは知ったことではない。 でも、土方がここにこうやってわざわざケンカを買いにくる理由は知っているのだ。 そもそもが最初から最後までケンカをしてるような仲だったのだから、やれるものはこれくらいだ。あいつだってきっと、本望だろう。 にやっと笑って、起き上がり、大声で返事をするのだ。 (最初から最後までケンカ) 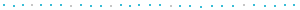 先週風邪をひいてからというもの、土方が妙に優しくて、治ったはずなのに少し寒気がする。 「なんでまたそんなもん……」 「こういうの好きだろ」 机に置かれた白いケーキの箱が眩しい。なんてったって有名ケーキ店の名前を冠した箱だ。 この中にいくつケーキが入っていて、いくらしたのかは知らないが、絶対に美味いということは知っている。 「もう風邪治ったけど」 「そんなの別に関係ねーよ」 しれっとした顔で土方は言うと、勝手に灰皿を出してタバコを吸う。暮れはじめた陽がその鼻梁に当たっている。 その余裕が何だか憎い。つい、風邪をひいて身動きが取れないからって頼みごとなんかしたのが間違いだったのだ。 甘えることなんて、めったにないからきっと嬉しかったのだろう、このバカは。 「……甘やかしてんじゃねーよ」 小さな声で言うと、土方はそのしれっとした顔をこちらに向けて、返事をした。 「お前なんかどろっどろに甘やかして、俺から離れられなくしてやるよ」 短くなったタバコを灰皿に押し付けると、少し得意げに笑う。やっぱりバカだ、と思って目を逸らす。 ケーキを早く冷蔵庫にいれないといけない。箱をそっと持って立ちあがる。 「あのさぁ、土方君? 甘やかすのもいいけど、反逆されたって知らないかんね?」 箱を両手で持ち、席を立つ。台所に向かうために廊下へ出るその前に、土方の傍に寄る。 怪訝そうな顔へ、銀時は唇を近づける。舌先で土方の唇を嘗めて、近い黒い瞳をじっと見る。 「これ、ケーキ一個分ね」 「……あと、七個分、期待してるぜ?」 何とかそう言った土方の顔が赤いので、やっぱりこいつはバカだなあと、結局愛おしくなるのだ。 (「お前なんかどろっどろに甘やかして、俺から離れられなくしてやる」) 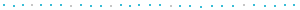 「兄弟なんてめんどくさいもんだな」 「まあな」 路地は狭く暗いので、声はその親密な湿度によく馴染んだ。新八も神楽もそうだが、土方にも兄弟がいたのだななんて、ぼんやり思う。 銀時にとっては未知の存在だ。それこそ、兄弟どころか、親も、家族も真似ごとしか知らないけれど。 「それでも、悪かねぇよ」 土方は少し目を伏せて呟く。タバコも吸わない、眉間の皺もない、刀を抜いたり、大げさに怒ったりもしない。 そのどれももうすっかり慣れて、対応方法も十分知っている。だが、今のこの目に合うような言葉を持っていないことに、銀時は心底後悔した。 「……今のお前の素、みたいな」 「かやくご飯の素、みたいに言うな」 くっと土方が笑ったので少しだけ、良かったと思った。その笑顔もすぐに消えたので、どうしようかなと珍しく頭がよく回転する。 でも家族だとか、そういうものに対してポンコツなのでうまい答えは出ない。しょうがないのかもしれない。 しょうがないので、元から対して離れてもいなかった距離を詰めて、両腕を広げてみる。そのまま体に腕をまわして、力を込めても、 土方が抵抗しなかったので、まあいいかな、なんて思う。 たぶんこうやって少し俯くことで、土方は涙を見せないつもりでいるのだろう。それはそれで悔しい気もするが、そのプライドは分かるので黙っている。 土方は黙っていたが、しばらくして銀時の頭をわしわしと撫でる――というより乱すの方が正しいかもしれない――と悪い、と一言だけこぼした。 「兄弟にも親にも恋人にもなれないけどね」 「それでいいんだよ、てめーは」 また少し土方が笑ったので、安心している自分がいる。 (涙は見せないで) 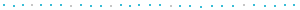 書類に埋まっている畳の一角だけが、切り取られたように自由空間なのが気に食わない。 「何やってんだてめーは」 「ここ空調効いてるからね」 「からなんだ、おめーの休憩室じゃねーんだぞ」 その言葉にうん、なんて適当な返事をして銀時は寝がえりを打つと、手のジャンプを一ページめくって、さぞおかしそうに笑った。 「ふは、あ、土方が仕事終わるの待ってるんだからさ、いいじゃねーの」 「……今日中にはたぶん終わらねぇぞ」 銀時はじゃあ、と言う。まだジャンプを閉じる気配がない。この部屋に入ってからというもの、銀時と目があっていないような気がする。 「これ読み終わったら帰るわ。ま、仕事のあるうちは、真面目な土方はこっちがどんなに待ってたって、手なんか出せないもんな」 歯を見せてわざとらしく笑って、もう一度寝がえりを打つ。うつ伏せから仰向けになって、喉をさらして、ゆるゆると笑って見せてくる。 ああ、挑発か、なんて頭がゆっくりどうする、と自分に問いかけてくる。どうしようか。仕事は山積みだが、これは確かに据え膳だろう。 そして舐められているのなら、それをひっくり返すのも楽しいかもしれない。 余裕の笑みでジャンプを手放した銀時に近づいて、その笑みが消えないうちにマウントポジションを取る。 「え、なに土方」 「挑発されたから襲ってみることにするわ」 「は、えええ、ちょちょ、いやいや冗談だし」 「もう遅い」 手元にある上着のジッパーを下していく。うろたえている顔なんてそうそう見られないので、じっくり見ておくことにしよう。 その顔を思い出せば、山積している仕事だって手早く終えられるに違いない。 (挑発されたので襲ってみることにする) 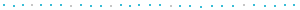 思い出や過去はなんだと聞かれたら、風呂だと答える。暖かいが冷めるし、温度はその時によってまちまちだ。 長く浸かっていれば少し疲れるし、眠くもなるし、手も皺が寄る。いいことばかりでもない。 現在は、海だ。冷たい時もあれば心地よい時もある。波に乗って泳げば強くもなるし、遠くへも行ける。 「未来は」 「宇宙だな」 上に指させば、土方はその心は、と聞く。 「何にもないけどなんかある。可能性、じゃねーの」 「ま、道理か」 土方は笑うと少しだけこちらを向いて、布団の中に戻した銀時の手を掴んだ。暗い部屋の中は、しんとして暖かい。 このままこの部屋ごと宇宙に放り出されても、たぶん後悔できない、と思って土方の手を強く握った。 「どうした?」 「怖い」 「何が」 顎まで布団にもぐると、返事をしないでただ静かに息を吸った。こんなくだらない話を、こんな汚い部屋の、綺麗でもない布団の中で。 きっと世界どころか宇宙中探したって、土方のような奴はいないだろう。こうして隣に当然みたいな顔をしていてくれるような奴は。 「波に乗ってずいぶん遠くまで来ちまった」 「海だから仕方がねーだろ」 暖かな海の中にいて、それはたぶんきっと幸せなことだ。遠く、昔の自分がいた頃の島は、国は、美しく、やはり遠い。 時々心を洗いに行く程度の、そうだ風呂で良いのだろう。 「遠くまで来たけど、ま、お前に会えたからいいよ」 それだけ言い捨てて、布団に今度は頭まですっぽり潜り込む。流れ着いた君の島が、優しく暖かであったことを感謝しながら、眠りにつくのだ。 (土←←←銀) -------------------------------------------------------------- 12.02.12 最後のカッコの中はいただいたリクエストお題でした。 SpecialSweetStupidは冊子の名前にしてました。 すごく甘くてあほという意味です。 |