|
目が覚めて、ふと卵焼きが食べたい、と思った。 起き上がって障子から見える日の傾きで、もう午前も終わる頃だと気付いた。 今日は非番だから構わないが、銀時が周囲にいないことに、寝起きの頭 で不思議に思う。 実を言うと、ここは万事屋の銀時の部屋だ。 銀時が自分より早く起きて、さらにこちらを起こさないのは珍しい。 布団から抜け出て襖を開けると、台所から物音がした。銀時だろう。 歩み寄って、シンクに向かう背中に呟いた。 「卵焼き喰いたい」 「おはようさん。なに?珍しいね、土方がリクエストするとか」 「甘いやつがいい」 「……ふうん、わかったけど。顔洗ってこれば?」 冷蔵庫を開けて、卵を取り出しながら、銀時は躊躇のない手つきで料理をこなしていく。 その姿に曖昧に返事をして、洗面所に向かった。 子供たちのいない万事屋の朝は静かでひんやりと冷たく、それが心地よかった。 顔を洗って戻ると、銀時がフライパンを傾けて卵焼きを巻いていた。 薄く焼き色の付いた、黄色い薄っぺらな卵がくるりと転がる。 見てる間に完成し、手際よくまな板に置かれ、同じ幅に切りそろえられる。 一番端の部分を銀時はひょいと取る。 「ん」 差し出されたそれに口を開ける。指先が唇に触れて、卵焼きはほろりと甘かった。 銀時はこちらをじっと見て、ふと笑った。 「うまい」 「そー?」 銀時のいつも作る卵焼きは甘くない。そして思い出す。 見た夢に、ミツバが出てきたことを。土方は舌の上の甘さを飲み下す。 「うまいよ」 それに、銀時はうん、と返事だけして笑った。 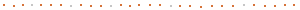 「ちょ土方、いいとこ来た、お前これちょっと預かってて! 「はあ?」 道端であった銀時にぽいっと渡されたのは、まだ言葉も儘ならない子供だった。 「おいっ銀時!」 「でけぇ声出してんじゃねーよ泣いたらどうすんだ!」 叫び返しながら銀時は、すぐ近くの公衆トイレに走って行った。 ああなるほど、と思いながら、腕のなかの少し温度の高い生き物を見て、ぞっとした。 「そっくりじゃねーか……」 「あぽん」 そっくりのふてぶてしい表情にうねって色素の薄い髪。 なんだかそれだけで喋れもしないのに、憎まれ口の一つも言いそうな気がしてくるから不思議だ。 ふにゃふにゃと柔らかくて頼りない、人間として未熟なそれを不得手としていたはずなのに、 銀時にそっくりというだけで、大丈夫な気もしてくる。 「もしかしてお前、あいつの隠し子か」 「ちーがーいーまーすーうー。なあ、勘七郎」 容赦なく頭を叩かれてやっと、銀時が戻って来ていたことに気付いた。 ひょいと土方の腕から子供を受け取ると、銀時は慣れた様子で腕に抱えて、 そのガキの顔を覗き込んで笑いかけている。 「知り合いの子供預かってるだけだっつーの」 「本当か?」 「あんなガキ二人もいんのに自分のなんかいらねーよ」 「それがお前のガキでもいいかと思ったんだよ」 「ちょっそれどういう意味?」 悪くないと思ったんだ。こいつならいいかと思ったんだ。 自分だったら無理だと知っていて、それでも傍にいるのに。 「意味わかんね、なあ」 その呼びかけに、銀時の腕の中の子供は素知らぬ顔をしている。 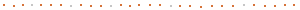 沖田が、右手に見慣れないものを持っていた。 すい、と右手をあげるのと同時にひらりしゃらりとそれは揺れて、儚げに光った。 「こんなの落ちてたけど、誰のですかねィ」 それはかんざしだった。鮮やかに赤い飾り玉が付いていて、いかにも若い女がしていそうなものだ。 それを指先でつまむように持ち、光にかざしている。透明に光を反射してそれが沖田の顔の上で踊る。 ちらりとこちらを見る。何が言いたいのかは大体分かる。 「なんだ、俺に女でもいるって言いたいのか?」 「じゃなかったら、こんなの誰が持ってんですかィ」 「ちげェよ。屯所に女なんか連れ込むか」 ふうん、なんて曖昧な返事をしながら、沖田はまだかんざしを指先でゆっくりと回しながら眺めている。 「あ、ザキ」 廊下を小走りでやってきた山崎は、沖田の前を素通りして、すぐ横に膝をついて紙束を置く。 「副長、これ頼まれてた資料っす」 「ああ、これ終わったやつだから持ってけ」 はいよ、と山崎は返事をすると持っていた他の資料にそれを重ねて、ひょいと立ち上がる。 「沖田さんもさぼってないで仕事してくださいよ」 「山崎のクセにうるせェなあ」 沖田の一言に少し山崎は顔をしかめたが、少し肩をすくめただけで、いつもの表情に戻った。 そして淡々と言う。 「あと、それ俺のですから」 沖田の視線が指先のかんざしに落ちる。 壊さないでくださいよ、と告げると、山崎はそのまま荷物を抱えて行ってしまった。 かんざしはさっきと変わらず平然と陽光に輝いている。沖田の指先を自分も見ながら、何となく呟いてしまう。 「あなどれねーな、あいつも」 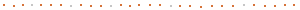 残った腕は、ひんやりとしていた。 「一本しかないなんて笑っちゃうよね」 「あんたが一本にしたんだろうが」 露骨に嫌な顔をした阿伏兎は、そんな顔をしながらも、掴まれた手を離そうとはしなかった。 「こうやってなくなってから考えたりしない? 両腕でできることってこんなにあったのかとか、もうできないこともあるとか、 そういうの、阿伏兎は考えない?」 「そりゃあ、思うさ」 「そう」 その答えに満足だったので、神威はため息をつくようにゆっくりと返事をした。 戦ってしか生きていくことのできない種族としては致命的な欠陥だろう、腕が一本しかないということは。 そのことで、阿伏兎が苦労をすればいい。面倒だと思えばいい。たくさん、たくさん。 腕がないせいで思うもうできないことや不便や、危険や死やそれに至る恐怖まで全て、 自分があたえたものなのだ。そのことが、やたらと満足でたまらない。 もう一度、ため息をつくのと一緒に呟く。そう、とだけ。それに、阿伏兎はもう眉をひそめたりしなかった。 ただこちらを見て言う。 「このすっとこどっこいが」 「なんで?」 「あんたの考えてることなんか、お見通しだよこっちは。簡単に死んだりしねえからな」 「そうでないと、困るな」 その間もやっぱりずっと、手は離れなかったし、その手は冷たいままだった。 自分自身の手も同じくらい、冷たかったのだけれど。 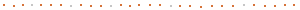 「痛くないからいんだよ」 「そういう問題か」 違うけど、なんて笑って銀時は服のジッパーをあげた。 腹部の包帯は隠れて見えなくなってしまったけれど、その白い色が目に焼き付いて取れない。 「死なない程度に留めてんだから良いだろ」 「よく言う……」 何度も死にそうになってるのを、何とか生き留めているの間違いだろう。 それを口に出したところで銀時はこともなげに、簡単なはぐらかしを言い、自分は黙らざるを得ないのだ。 土方にとってそれほど腹立たしいこともない。 それで結局黙っているから、肺の底に雑な言葉に包まれたままの心配という物質が、よどんで溜まっている。 腹立たしい。土方が無表情に怒っていることを、銀時は百も承知でいるのも、それに拍車をかける。 「お前なんか、」 「うん、知ってる」 「続き言わせろよ」 遮られたことはうっとうしかったからとか、わかりきっているからではないも知っている。 それも腹立たしい。 「ごめんね」 そんなんが聞きたいんじゃない。少しうつむいた銀時の顔に逆光で光が当たっている。 髪は透けて光る。表情が見えない。 土方は泣いてるんじゃないかと思って、頬に手を伸ばしたけれど、触れた指先は乾いていた。 それがさらに腹立たしいのに、こっちが泣きたくなるからずるい、と言葉には出さないけれど思った。 「ばかやろう」 「うん」 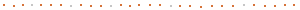 好きなものとか嫌いなものとか、そういう区別が昔っから少し曖昧で、 一番を聞かれたらなんだかはっきり答えられずに、自分で自分に困惑するというのをよくしてきたけれど、 神楽はそのことを笑わなかったし、少しわかる、と言った。なんだかよくわからなくなる時がある、と。 なんでもかんでもポーズに感じる、なんて言った。その言葉をもらった時、彼女の初めて手に触れた。 もしかしたら嬉しかったのかもしれない。 沖田はただ黙って隣に座って、そのくせがっぷり四つに組まれた指同士を見下ろす。 小さい、と思う。小さい手。神楽はそうやって自分の手が見られていることに気付かず、 さっきと変わらずぼんやりと前を見ている。 「なあ」 「ん?」 神楽がこっちを向く。そっと、できるだけそっと指に力を入れる。組まれた指が暖かい。 思考がはっきりとしてくる。 「好きなものあった」 「なにアルか?」 少し笑って、神楽は期待を込めたようにゆっくりと聞いてくれた。 「これ、こうやってんの、好きだ」 繋ぎ合った手を緩やかに揺らすと、神楽がうなずいた。 「よかった」 「何が?」 「そーごにも好きなことあってよかった」 足元の影が、一つに繋がっているのが少し不思議な形で、でもそれが正しいような気がした。 -------------------------------------------------------------- 12.05.20 2011年の春から、2012年の春まで使っていた拍手のお礼6種です。 リクエストいただいたりして書きました。 少しでもお礼になっていたら幸いです。 |